近年、建設業界で頻繁に聞くようになった、openBIM、OpenCDE、OpenAEC…。「とりあえずBIMで」「発注者からIFCでの納品が必須になった」といった言葉が飛び交う現場も、もはや珍しくありません。しかし、その裏で多くの担当者がBIMの課題に直面しています。「これ、本当に効率化になってる?」――もしそう感じているなら、それはあなただけではありません。本記事では、オープンBIMの理想と現実のギャップ、そして多くの現場が抱えるBIMの課題の根本原因を、少し辛口な視点も交えて掘り下げ、明日からできる解決策を提案します。
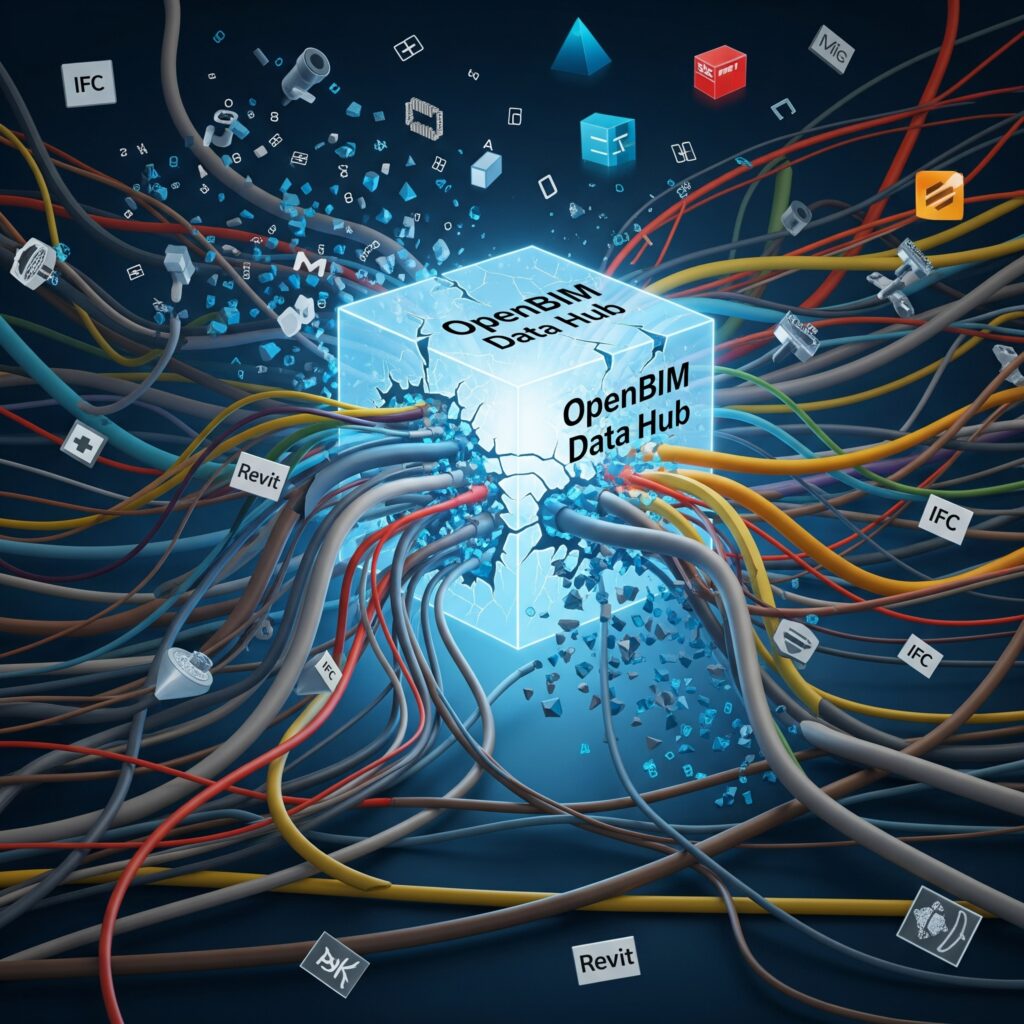
近年、業界で頻繁に聞くようになった言葉があります。
openBIM、OpenCDE、OpenAEC…。
「とりあえずBIMで」「発注者からIFCでの納品が必須になった」 こんな言葉が飛び交う現場は、もはや珍しくありません。3Dモデルが飛び交い、VRでの打ち合わせも当たり前になりました。まさにBIM 建築を中心に、建設DXの真っ只中です。
しかし、BIM推進室や現場の担当者の皆さんが直面するのは、逆に増える無駄な作業。
「IFCデータのエラー修正に、一晩かかった…」 「結局、施工図はゼロから書き起こしている…」 「これ、本当に効率化になってる?」
「オープンBIM」「データの民主化」――。そんな華やかなキーワードとは裏腹に、むしろ仕事が増え、現場が疲弊している。もしそう感じているなら、それはあなただけではありません。
今回は、なぜ理想通りにいかないのか、そして変革のために本当に必要なものは何か、少し辛口な視点も交えて掘り下げてみたいと思います。
「オープン」の実態と現実の裏側:IFCは本当に業界を変えるのか?
IFC(Industry Foundation Classes)は国際標準で、発注者から「IFC納品」を求められることも増えました。
しかし、実態はこうです。
なぜ?①:「オープン」の皮をかぶった、新たな「囲い込み」
「特定のベンダーに縛られない、オープンな環境を」 この言葉に、私たちはどれだけ期待したことでしょう。しかし、現実はどうでしょうか。
例えば、ある現場で「オープンな共通データ環境(OpenCDE)」を謳うA社のクラウドサービスを導入したとします。確かに、IFCやBCF(BIM Collaboration Format)といった標準フォーマットに対応し、誰でもアクセスできる「はず」でした。
しかし、実際に運用してみると、A社のBIMソフトとの連携は驚くほどスムーズなのに、競合であるB社のソフトからアップロードしたIFCは、なぜか属性情報が一部欠落する。結局、スムーズな運用のためにはA社のエコシステムで固めるのが一番楽になり、気づけば新たな「ベンダーロックイン」の完成です。
そして、「オープン」は「無料」でも「万能」でもありません。 その裏には、標準化の主導権を握り、自社のプラットフォームを業界標準にしようとする各社のビジネス戦略があります。私たちはその事実を冷静に理解し、「誰にとってのオープンなのか?」を見極める視点が必要です。
なぜ?②:IFCは「文化の壁」を越えられない
問題はツールだけではありません。むしろ、こちらの方が根深いかもしれません。
先日、あるゼネコンのBIMマネージャーがこぼしていました。
「設計事務所さんから、それは見事なIFCデータが納品されたんです。構造から設備、建具の属性情報まで完璧に。でも結局、うちの施工担当はそれを横目で見ながら、使い慣れた2D-CADで施工図を”再作成”している。宝の持ち腐れですよ」
「結局、3Dで全て完結できるわけがなく、3Dで表現できないものもたくさんあります。たとえば、ドアの開口部の大きさなり、抽象的な空間表現なり。IFCによってその部分の欠落がまさに業務に直接影響されています。」
なぜ、こんなことが起きるのでしょうか? 理由は単純です。データは交換できても、仕事の進め方や責任の所在といった「プロセス」は交換できないからです。
- 責任の壁: 設計IFCデータをそのまま使って施工し、もし問題が起きたら誰が責任を取るのか? 従来の契約形態では、施工側がリスクを負うことになるため、「自ら作図した、責任の持てる図面」でなければ仕事を進められません。
- 情報の壁: 設計データには、仮設足場の計画やコンクリートの打設順序といった「施工側の情報」は含まれていません。結局、施工側で情報を付加・再構築する必要があるのです。
結局のところ、IFCは「最終成果物」として契約書にハンコを押すために存在するだけで、日々の業務プロセスに溶け込んでいない。
IFCは必要最低限の“共通語”にはなるけど、業界のワークフローそのものを変える力はない。
これが多くの現場の実態ではないでしょうか。データ形式という技術的な問題の裏には、縦割りの組織、多段階の請負構造、そして旧来の契約形態という、強固な「文化の壁」が横たわっているのです。
そこに、VDCが登場すべきです。

なぜ?③:BIMはIFC納品用止まりになってしまい、本当に実現したい「生産性向上」に全く関係ない
設計、施工、維持管理。それぞれのフェーズが契約や組織で分断されている日本では、BIMデータはバトンのように受け継がれません。
- 設計BIMは「参考図」: 施工者は、責任問題や情報不足から、設計BIMをそのまま活用せず、結局「参考図」として扱い、施工用のBIMや図面を再作成します。
- 施工BIMは「納品物」: 工事中の膨大な情報が詰め込まれた施工BIMも、検査・納品が終われば、その役割を終えます。維持管理フェーズで活用されることなく、サーバーの奥深くで眠りにつくのです。
各プレイヤーが自分のフェーズでの「納品」というゴールテープを切ることしか考えていない。これではデータが資産として川のように流れるはずもなく、フェーズの境界で澱み、「死んだデータ」になってしまうのは当然です。
では、明日から何をすべきか?
「実用や文化が問題だ」と言われても、一担当者に何ができるのか、と途方に暮れてしまいますよね。しかし、現場レベルでできることは確実にあります。
ステップ1:「目的」を問い直す
まず「IFCで納品すること」が目的になっていないか、自問してみましょう。「このBIMデータを使って、何を解決したいのか?」を具体的な言葉にするのです。 「設計段階で、建築と設備の干渉を90%潰し込む」 「躯体数量をモデルから直接拾い、積算の手間を30%削減する」 目的が明確になれば、そのために必要なデータの仕様やルールも自ずと見えてきます。
ステップ2:「小さな合意形成」を始める
プロジェクト全体で完璧なデータ連携を目指すのは、あまりに壮大です。まずは、顔の見える関係者の中で「小さな成功事例」を作ることから始めましょう。
例えば、「今回のプロジェクトでは、建築と設備の取り合いについてだけ、毎週月曜の午前中にIFCでデータ交換し、〇〇(ツール名)上でBIM調整会議を開く」という、ごく具体的なルールをBIM実行計画(BEP)に落とし込むのです。 この小さな成功体験が、関係者の信頼を育み、次のステップへの足掛かりとなります。
ステップ3:ツールより文化と「対話」を優先する
最新のツールを導入する前に、やるべきことがあります。それは関係者が顔を合わせ、「このデータは何のために作るのか」「受け取った後、どう使いたいのか」を徹底的に対話することです。 「この属性情報を入れてくれれば、積算がすごく楽になる」「その表現だと、現場で誤解が生まれる」 こうした泥臭いコミュニケーションこそが、データの価値を決めます。
技術的な問題の多くは、実はコミュニケーションの不足が原因なのです。
Openは、ツールではなく、文化です。
常に情報の透明性を重要視し、会話する。何か問題があったら責任を問うではなく、解決策を一緒に考える。それこそBIMが本当の意味だと思います。
まとめ:DXの主役は、皆様自身だ
建設DXの主役は、BIMソフトやIFCといった技術ではありません。それを使いこなす「人」であり、円滑な協業を実現するための「プロセス」と「ルール」です。
業界全体の変革は、契約や文化といった大きな話に行き着きます。しかし、その壮大な物語の第一歩は、現場にいる私たち一人ひとりが、隣の部署や協力会社と交わす小さな対話から始まるのかもしれません。
革新的なテクノロジーソリューションで、建設業界の未来をつなぐ
- データ戦略立案・活用支援
- 建設業務改善コンサルティング
- 工業化建築
- ソフトウェア・システム開発


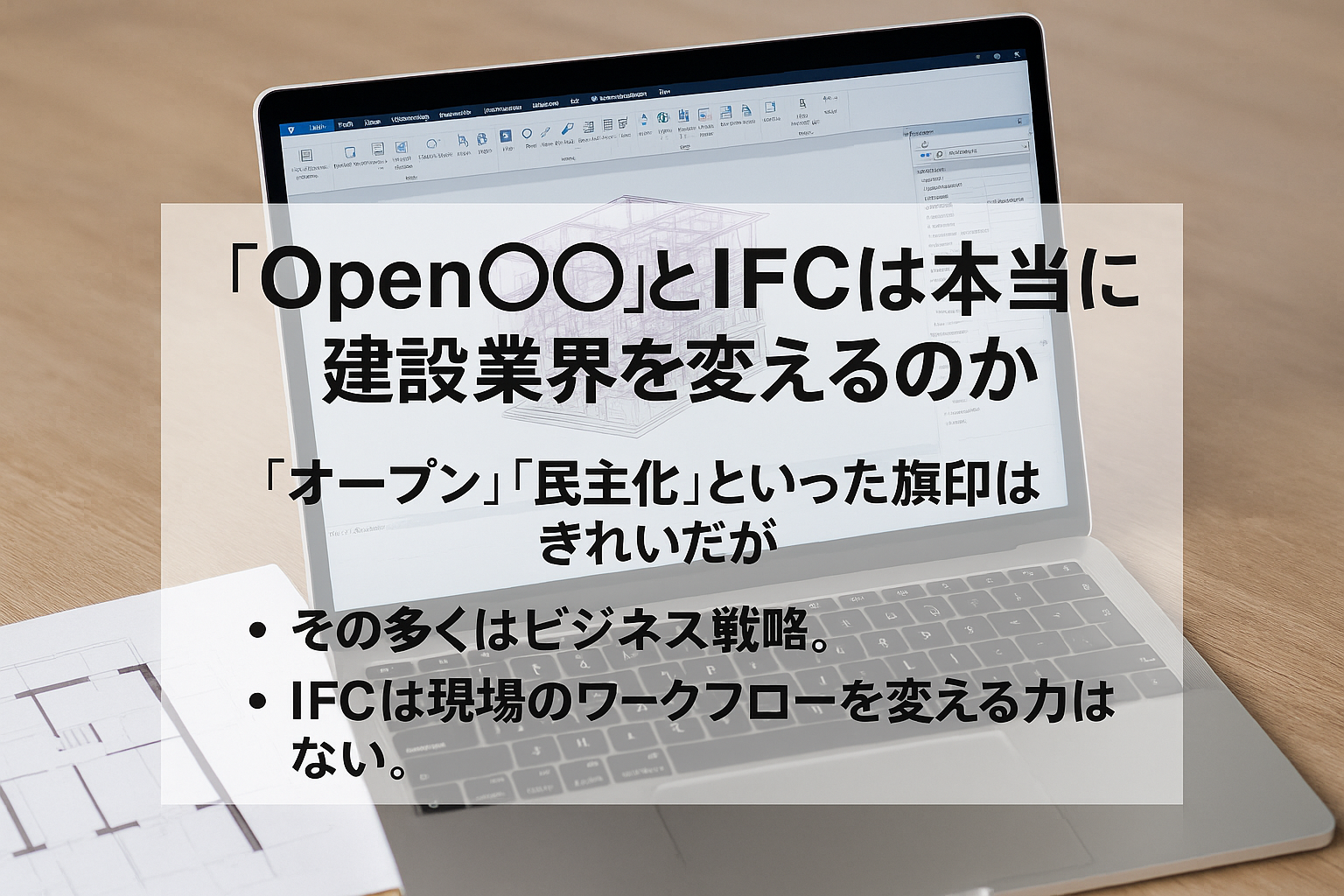
コメントを残す